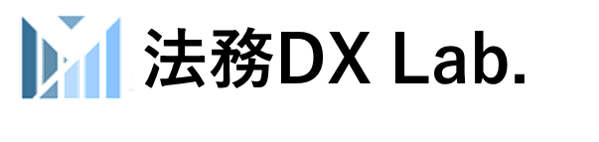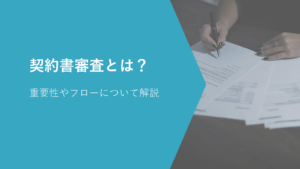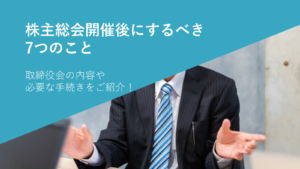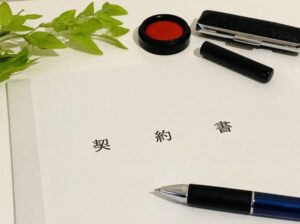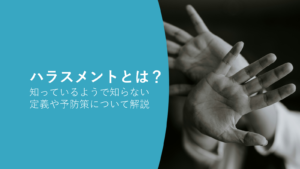【ダウンロード可】覚書のテンプレートをパターン別に用意!書き方も解説
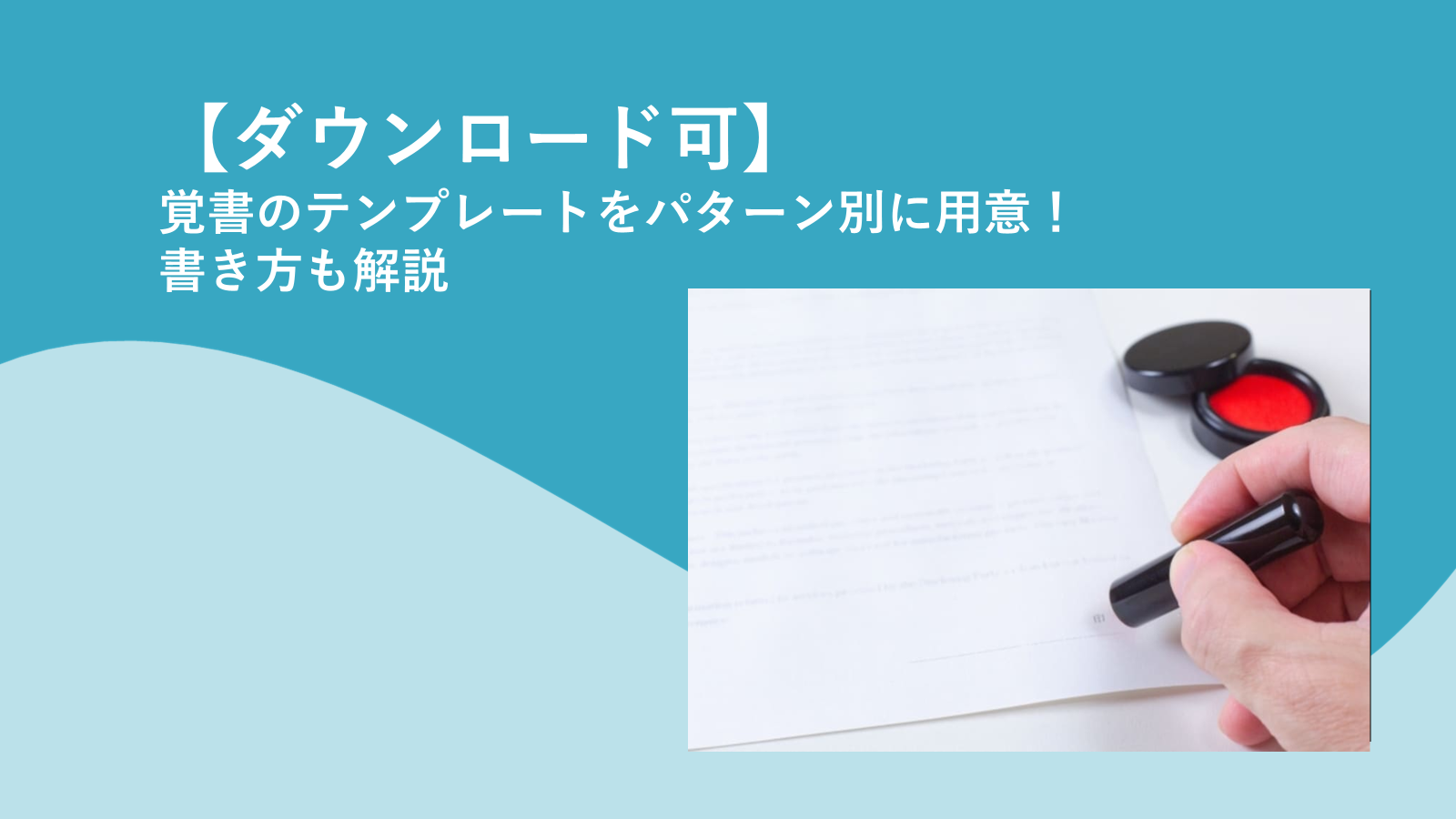
契約書の内容を補完する目的などで取引先と覚書を締結する場面は少なくありません。
しかし、契約内容によって盛り込む条項がある程度決まっている契約書とは異なり、覚書は内容を変更する部分だけ記載するなど、本文の形態がさまざまです。
そこで、本記事では用途に応じた覚書のテンプレートをダウンロード可能な形で提供し、各部分の記載方法を解説します。
覚書の書き方を具体的に知りたい方は、本記事を最後まで読んでみてください。
こちらページ下部の申し込みフォームから無料でダウンロードいただけますので、よろしければご覧ください。
そもそも覚書とはどのようなものか、具体的に知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
関連記事はこちら
売買金額を変更するときの覚書のテンプレート

契約締結後に覚書で売買金額を変更する際、覚書本文に『原契約第〇条の売買代金について「金〇円」を「金△円」に変更する。』などと記載しましょう。
覚書によって原契約のどの部分を変更したか明確にするため、「本覚書に定めのない事項については、原契約の定めに従うものとする。」などの条項も盛り込みます。
売買代金などの契約金額を変更する契約を締結する際は、変更前後の金額を明記し、増額または減額となった金額がいくらであるかわかるようにすることが必要です。
変更前後の金額または、変更前の金額をいくら増額させるかが明記されていないと、印紙税において変更後の金額が、記載金額として扱われる可能性があります。
変更前後の差額が記載金額として扱われるためには、変更された金額が明らかな覚書を作成しなければならないため、注意が必要です。
契約期間の変更を覚書で取り決める際のテンプレート
契約期間を覚書で変更する場合、覚書本文に『原契約第〇条の契約期間について「令和〇年〇月〇日から令和△年△月△日まで」を「令和×年×月×日から令和□年□月□日まで」に変更する。』などと記載しましょう。
前章で解説したように、覚書で原契約のどの部分を変更したか明確にするための条項を盛り込んでおくとよい点は同様です。
また、契約期間を延長する際は、印紙税の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合、1通につき4,000円の収入印紙が必要になります。ただし、契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは対象外になるので、締結前によく確認しておきましょう。
契約当事者の変更について覚書で定めるときのテンプレート
契約当事者の名称を、吸収合併や事業譲渡、社名変更などで変更する際の覚書の書き方を解説します。ただし、社名変更や吸収合併などの場合、覚書は必ずしも作成する必要はありません。
社名変更(商号変更)を行っても法人格は変わらないためです。吸収合併についても会社法第2条第27号で「合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの」と規定されています。そのため、関係会社への通知を行うだけの場合もあります。
しかし、社名変更などによって確認が煩雑になることから、当事者間で覚書を締結することは可能です。この場合、契約者名義を変更することとなった旨や、変更前後の契約者の住所や会社名などを記載します。
今回は事業譲渡によって、契約上の地位を譲渡先へ承継する際の覚書を、ダウンロード可能なテンプレートとして用意しています。事業譲渡によって契約上の権利義務を承継する場合、覚書で事業譲渡があったことと、その効力発生日を記載し、契約の相手方に対する契約上の義務を譲渡先が引き継ぐことを記載しましょう。
覚書テンプレートを基に書き方を解説

ここまで紹介してきた覚書のテンプレートを基に、覚書の各部分の書き方を具体的に解説します。具体例を挙げて解説するので、覚書の書き方に迷っている方は参考にしてみてください。
覚書の次の部分について、詳しく解説します。
- 表題
- 全文
- 本文
- 有効期限
- 後文
- 署名・捺印
それぞれ順番に見ていきましょう。
表題
表題(タイトル)は、「〇〇についての覚書」や「〇〇に関する覚書」として、どのような内容について取り決めを行ったものか、第三者が見てもわかるようにしておくとよいでしょう。
明確な決まりがあるわけではないため、単に「覚書」としても問題はありません。しかし、検索性が下がるうえに、複数の覚書を締結した際、内容を把握しにくくなります。
また、覚書が契約内容の変更や補完を目的とするものである場合、「〇〇についての変更契約書」などとしても、法的な効力に違いはありません。
前文
前文は、契約書と同じように契約当事者を「甲」、「乙」と略し、どのような目的で覚書を取り交わすのかを記載します。
既に取り交わした契約内容の一部を変更する場合など、基となる契約があれば、どの契約かわかるように契約日と表題を記載しましょう。このとき、何度も契約日と表題を記載することを省略するために「原契約」と略すのが一般的です。
【記載例】
株式会社〇〇(以下、「甲」という。)と、株式会社△△(以下、「乙」という。)は、令和〇年〇月〇日に甲乙間で契約した〇〇契約(以下「原契約」という。)について、下記の通り変更することを合意した。
本文
本文では、覚書によってどのような内容を契約当事者間で取り決めるのか、記書きの中に記載します。前文の後に「記」と「以上」を設け、その間に本文を入れます。取り決める内容が複数ある場合は、第1条、第2条と条建てを行い、簡潔に記載しましょう。
また、原契約から変更を行う場合、原契約のどの部分について取り決めを行うのか、原契約の条項を示して、当事者間で認識の相違がないようにします。
【記載例】
第1条(売買金額の変更)
原契約第〇条の売買代金について「金〇円」を「金△円」に変更する。
第2条(原契約の適用)
本覚書に定めのない事項については、原契約の定めに従うものとする。
有効期限
覚書で取り決める内容に有効期限を設定する場合や、原契約で定められた有効期限を変更する場合に本文中で定めます。有効期限は覚書の必須項目ではないため、必要に応じて盛り込みましょう。
有効期限を定める場合は、条建てをして、「本覚書の有効期限は、令和◯年◯月◯日から、令和◯年◯月◯日までの満◯年間とする」などと記載します。
後文
後文は、本文の「以上」の後に記載し、覚書を何通作成し誰が保有するかを定めます。文言はある程度決まっており、契約書の後文と書き方はほとんど同じです。
紙で覚書を作成する場合は、「本書面2通を作成し、甲乙両者署名捺印の上、各1通を保有する」などと記載します。電子契約の場合、「本書の電磁的記録を作成し、電子署名を施した上で、各自その電磁的記録を保管する」のように文言を置き換えます。
【記載例】
本覚書締結を証するため、本書面2通を作成し、甲乙両者署名捺印の上、各1通を保有するものとする。
署名・捺印
覚書を締結する日を記載し、契約当事者双方が署名・捺印を行います。
日付については、明確なルールはありませんが、契約書を作成した日や両者が商談の場で署名・捺印を行う場合は商談の日を記載します。覚書を郵送でやり取りし、それぞれが別日に署名・捺印する場合は、最後に行われる日を記載するのが一般的です。
また、西暦よりも和暦を用いて日付を記載することが多いです。
【記載例】
令和 年 月 日
(甲)
住所
会社名
代表者氏名 印
(乙)
住所
会社名
代表者氏名 印
契約書管理ツールで覚書をテンプレート化すれば効率化が可能!

覚書は取り決めの内容によって本文の内容が異なりますが、売買金額の変更などよく用いられる内容であれば、条文の内容をある程度使い回すことが可能です。電子契約にすればコピーが容易で使い回しやすく、印紙税もかからないため、課税文書に該当するか確認する手間も削減できます。
しかし、PDFファイルで保存すると、格納場所を探すのに時間がかかったり、基本的にファイル名でしか検索できなかったりと、不便を感じる場面も多いでしょう。
契約書管理ツール リーガレッジ(Legaledge)で管理すれば覚書の保管場所にも困らず、本文の内容から契約書の検索も可能です。
過去に作成した覚書をテンプレート化して、効率的に文書を作成することもできます。リーガレッジの仕様について詳しく知りたい方は、以下のページからご確認ください。