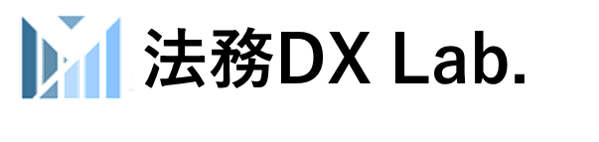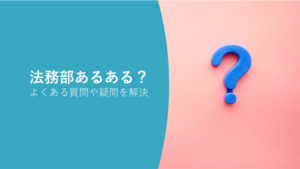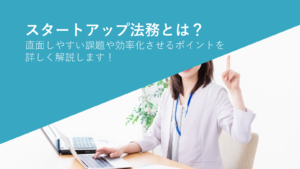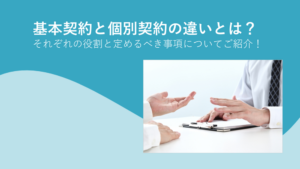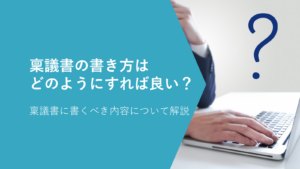NDA(秘密保持契約)とは?契約の締結タイミング、有効期間の考え方を解説
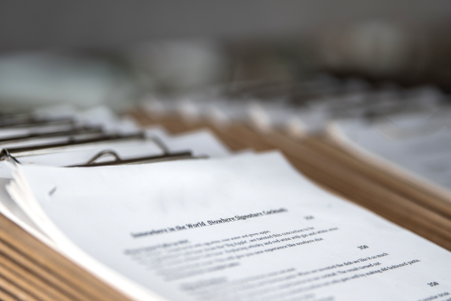
NDAには、有効期間に関する条項を記載するのが一般的です。また、期間延長や自動更新に関する規定を設けるケースも珍しくありません。そこで本記事では、NDAを締結する目的やタイミング、有効期間が必要な理由などについてわかりやすく解説します。
なお、以下の資料ではNDAを締結する流れやNDAの雛形、盛り込むべき条項などをわかりやすく解説しております。NDAについて網羅した資料となっておりますので、よろしければご覧ください。
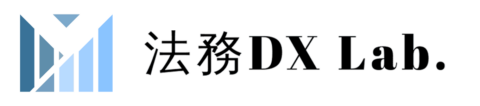
NDA(秘密保持契約)とは?
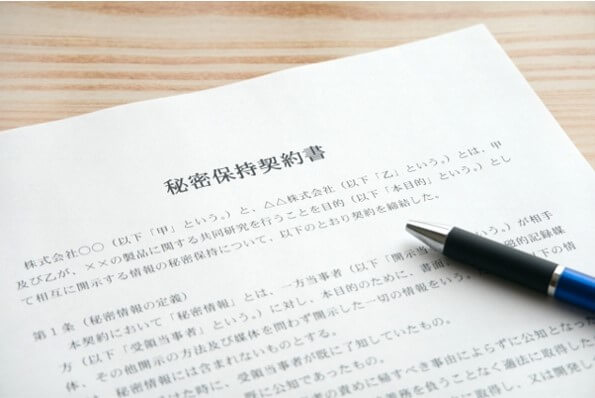
NDA(Non-Disclosure Agreement)とは、個人及び企業間で締結される秘密保持契約・守秘義務契約のことを指します。
秘密保持契約は、機密情報・個人情報の保護を目的として結ばれ、情報漏洩や、目的以外で情報を利用されないための事前対策として、重要な位置づけとされている契約です。
最近では、ビジネスで頻繁に交わされる契約のひとつとなっており、多くの方が締結した経験があるかもしれません。
似た用語に「機密保持契約」というものがありますが、これもNDAのことを指します。内容や法的効力に違いはありません。
NDAを締結する目的
企業がNDAを締結する目的には、ノウハウや顧客情報などの流出を防止することや、目的外の情報利用の制限、安定した契約交渉の環境確保などが挙げられます。
M&Aや業務提携・業務委託など新たに取引を開始する場合、通常、当事者同士でノウハウや顧客情報などの営業秘密を共有することが一般的です。これらの情報は、もしも外部に漏えいしてしまうと「市場での優位性が失われる」や「個人情報の漏洩」といった会社の不祥事につながる可能性も考えられます。
そのため、お互いに秘密保持義務を負うことによって、営業秘密が外部へ漏えいするリスクを最小限に抑えています。
また、業務上やり取りされる営業秘密は、当該取引の目的や範囲に限って適切に使われるべきものです。たとえば、取引先が持つ顧客情報を利用して顧客を奪うような行為は、信義則の観点から許されるものではないとわかるでしょう。このような目的外利用を防止する観点からも、NDAを締結します。
さらに、事前承諾がない目的外利用を禁止することによって、取引終了及び破談になった場合においても、提供した営業秘密を不正に利用されてしまうことを防ぐことが可能です。
秘密情報が漏えいすると、風評によって企業価値が変動するなど、契約交渉の環境が不安定になってしまうおそれがあります。お互いに利益となり得る取引を検討しているにもかかわらず、秘密情報が流出することによって、破談となるような事態は避けるべきです。
そのため、交渉開始前にNDAを締結することは、安定した契約交渉の環境を確保し、適切な情報管理を行う狙いもあります。
NDAを締結するタイミング
NDAを締結すべきタイミングは「自社の秘密情報を開示する前」が一般的です。
事前契約を結ばなかったときに起こり得るトラブルの例を挙げると、商談中に秘密情報を提供し、それが第三者へ漏えいしてしまったケースがあります。
このようなトラブルを防止する観点から、自社の秘密情報を相手へ開示する前に、NDAを締結することが重要です。
商談途中でまだ具体的な話が進んでいない段階では、NDAについて提案しにくいかもしれません。しかし、自社を守るには積極的に締結を求める必要があります。
もしも、相手が提案を受け入れない場合、協業するパートナーとして信用できない存在かもしれません。
NDAに有効期間が必要な理由
NDAが締結されると、情報を開示された当事者は秘密情報を適切に保管・管理するための方法を定めなければなりません。いくつか例を挙げると、以下のようなものが挙げられます。
- 記録媒体の管理場所を特定した上で、持出しが物理的に困難な状態にする
- 秘密情報を取り扱う従業員へ研修を実施する
- 十分なセキュリティを有したシステムを導入する
また、情報の内容や性質によっては、秘密として保持する必要性が生じない場合もあります。コスト・時間の経過による秘密情報の陳腐化などを理由として、NDAには一定の有効期間が設定されることがほとんどです。
NDAにおすすめのひな形
NDAにおすすめの雛形として、経済産業省が作成した雛形がございます。以下資料内では無料ダウンロードできるNDAの雛形をご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。
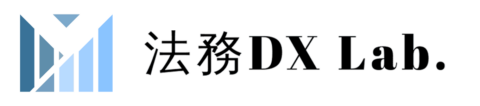
有効期間の設定で考慮すべき事項

NDAの有効期間を設定する際、考慮すべき事項は対象情報の性質によって大きく異なります。例えば、製品リリースの発表が予定されており、短期間で情報が一般的に知れ渡るケースでは、1年間などの有効期間が設定されることがほとんどです。
しかし、顧客情報のような重要性が高いものについては、5年などの有効期間や、有効期間の定めを設けないことも考えられるでしょう。つまり、秘密保持の対象となる情報の重要度に応じて定められる期間が変動します。そのため、情報ごとに重要度を判断し、相手方に期間のすり合わせを申し入れるようにしましょう。
つぎに、開示当事者側と受領当事者側の立場から見ていきましょう。
開示当事者側
有効期間を可能な限り長く設定しましょう。それに加えて、秘密情報が含まれた記録媒体の管理方法についても盛り込むように提案してください。
情報を保有する必要性がなくなったあとも、記録媒体を所有し続けると、情報漏洩・紛失するリスクが高まります。記載すべき条項の例には、以下のようなものが挙げられるでしょう。
- 求めに応じて記録媒体を返還する
- 求めに応じてデータを消去しなければならない
適宜、交渉を行い、情報の重要性に沿った条項を盛り込むようにしてください。
受領当事者側
提示された契約書の有効期間に関する条項の有無を確認してください。長期間の有効期間が記載されているような場合は、管理コスト・情報が漏洩した場合のリスクの観点から、なるべく短くなるように相手方と交渉するべきです。
さらに、契約終了後、一部の条項を存続させる条項が設定されている場合もあります。これは、契約終了後も秘密保持義務や損害賠償義務が一定期間存続すると定められていることと同じ意味がありますので、契約書に記載された条項を1つひとつチェックしてから締結しましょう。
NDA有効期間延長や自動更新の考え方

NDAの有効期間延長や自動更新の考え方には、以下の3つが挙げられます。
- 重要な事柄は無期限とするケースもある
- 公序良俗違反で無効となるケースもある
- 中途解約できる規定がないか確認が必要
ここからはそれぞれに分けて解説しますので、見ていきましょう。
重要な事柄は無期限とするケースもある
NDAは、有効期間を定めるにあたって法律上の決まりはありません。そのため、契約当事者間で自由に設定できます。
有効期間は、提供する情報の性質によって大きく変動し、重要な事柄は無期限とするケースもあり得るでしょう。具体的には、顧客情報や製品ノウハウ等の重要情報は、有効期間を無期限とするケースがほとんどです。
公序良俗違反で無効となるケースもある
契約内容が職業選択の自由を侵害していると判断されてしまうと、有効期限に関する条項が無効となるおそれも考えられるでしょう。
受領当事者にとって、長期間にわたって秘密情報の管理をしなければならないことは、管理コスト・情報漏洩リスクの両方から非常に大きな負担が伴います。
そのため、可能な限り有効期間を短く設定する・存続条項においても負担が軽くなるよう合意してもらうような交渉が必要となるでしょう。
中途解約できる規定がないか確認が必要
NDAに、有効期間の延長に関する規定を盛り込む場合、中途解約ができる規定がないか確認する必要があります。
NDAに中途解約を認める規定および、小さな義務違反をした場合に契約解除を認める条項が入っていると、有効期間や自動更新を設けた意味がなくなりかねません。
そのため、有効期間を短縮するおそれがある規定が書面に盛り込まれている場合には、削除を求めることも検討するべきしょう。
NDAの有効期間の管理は重要

NDAは締結する頻度が高い契約となっており、期限の管理においても煩雑になりがちです。
たとえば「A社とはNDA締結済みであったか」「B社とはNDA締結の内容が最新かどうか」「C社とのNDAはいつまで有効か」などが挙げられます。そのような悩みは、契約書の登録・管理からドキュメンテーションまでを一気通貫でサポートするクラウド契約業務DX化サービス「リーガレッジ」の期限管理を活用することで、管理業務を効率化できます。
また、お客様の現在の契約書管理状況に応じて最適な移行ソリューションをご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
NDAについてさらに詳しく知りたい方へ
NDAの雛形、締結までの流れや盛り込むべき条項などについて以下資料で詳しく解説しております。以下より無料でダウンロードいただけますので、よろしければご覧ください。