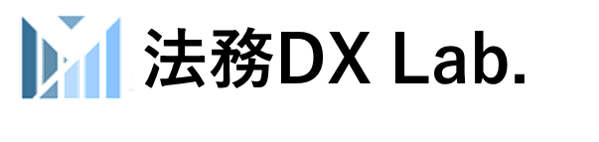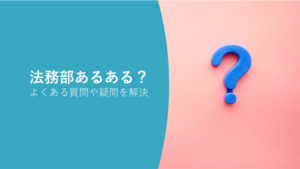BCP対策とは?策定方法や法務における必要性・想定事例を解説

BCP対策とは、企業が天災などの緊急時に事業継続を行うための計画のことをいいます。BCP対策は業種によっては定めることが義務となるため、各企業は対応を迫られています。法務部門においても決して他人事ではありません。特に昨今では新型コロナウイルス感染症の拡大で出社が困難となったケースもあり、こうしたケースで法務部門の業務をどのように継続するかというのは大きな課題となります。そこで、今回は法務部門の業務とBCP対策について想定事例を用いながら解説します。
BCP対策の定義と必要性

法務におけるBCP対策について解説する前にまずは一般的なBCP対策について簡単に解説します。
BCP対策の定義
BCP対策とは、Business Continuity Plan(事業継続計画)の略称です。BCP対策とは、大規模な自然災害や感染症の流行など、事業を継続する上でのリスクが発生した際に業務の中断などの被害を最小限に留め、スムーズに業務への影響を回復・復旧し、事業を継続する方法について定めた計画のことをいいます。
なぜBCP対策が必要なのか
昨今では大規模な地震や集中豪雨といった天災によるリスクだけでなく、コロナといった感染症の流行など様々な要因により、これまでと同様の事業継続が困難となる事態が発生しています。こうした状況に備え、事業の継続を可能にするためにBCP対策の実施が重要視されているのです。
BCP対策が注目された背景
では、何故BCP対策は注目されているのでしょうか。それには実際に日本で生じている災害とその頻度が関係しています。例として、2011年の東日本大震災の余震とされる地震が2021年2月と2022年3月に福島県沖で2回発生し、宮城県と福島県で震度6強を観測しています。その他の地域でも大規模な地震が観測されています。宮崎県の日向灘で最大震度5強(2022年1月)、茨城県沖で最大震度5弱(2022年5月)、石川県の能登半島で最大震度6強(2022年6月)を観測するなど大規模な地震が観測されています。また、地震だけではありません。大雨災害では、2020年7月の熊本豪雨、その翌年の2021年7月には東海地方・関東地方を襲った大雨の影響により熱海市で土石流の被害が発生しました。さらにその翌月の2021年8月には西日本を中心に記録的な大雨が発生するなど、災害については枚挙に暇がありません。こういった災害が実際に生じていることを背景に昨今ではBCP対策に注目が集まっているのです。
BCPとBCM、防災の違い
- BCMとの違い
BCMとは、「Business Continuity Management」の略で、事業継続マネジメントを意味します。BCPは事業継続計画であるのに対し、BCMは事業継続をするための体制づくりを指します。そのため、BCPはあくまでもBCMの一部であり、BCMはBCPを含む概念であるという点で両者は異なるということを押えておきましょう。
- 防災との違い
防災は一般的には災害を未然に防止したり、実際に災害が生じた場合には人の生命や財産への被害拡大を防ぐことを目的としています。そのため、企業の事業継続に重点を置くBCPとは目的をやや異にしているといえるでしょう。
BCP対策のメリット
BCP対策には以下3つのメリットがあります。
- 従業員と事業を保護できる
BCP対策を行うことで、従業員と事業を保護することができます。災害時に他社よりも迅速に事業の回復が可能となるため、取引先や顧客等からの信頼を確保することができます。特に災害時には取引先が倒産することで自社も倒産してしまう間接被害型の倒産も多く見られるため、こうした事態を防ぐことができるという点でも取引先から信頼を得ることが可能となります。
- 企業価値を高めることができる
BCP対策に取り組んでいるということは前述の通り緊急事態にも迅速に災害から復旧ができるという点で信頼が確保できるほか、事業と社員を重要視しているという点で大きなイメージアップにもつながります。
- 経営戦略を見直す機会になる
BCPの策定に当たっては、災害からの復旧の際に事業のどの部分を優先的に復旧させるのかといった優先順位の検討が必要になります。こうした検討を行う事によって自社の事業の重要な部分を再確認できるため、経営戦略を見直すことが可能となるというメリットがあります。
策定における4つのポイント

BCP対策を策定する際に抑えておきたいポイントを4つご紹介いたします。BCP対策においては、以下のような観点を持つことが重要です。
- 人的資源の観点
被災後に事業を復旧させる上では従業員等の人的資源が確保できることが必要不可欠です。そのためには被災時にどのくらいの従業員が業務に従事可能なのか安否などの情報を含めて把握し、従事可能な従業員のみでどの程度の業務が可能なのか、また出社できない従業員をどのように取扱うのかといった点などについてあらかじめ明確にしておきましょう。
- 物的資源の観点
法務業務も含め、会社の事業には設備が必要です。必要な設備や機器、どの業務に必要な設備を優先的に確保するのかといった物的資源の面も明確にしておく必要があります。また、設備や機器と関連して会社の情報もバックアップをして備える必要があります。物的資源や人的資源が回復しても情報が失われてしまっては、早期の復旧が困難だからです。そのためには、情報のバックアップをクラウドに保管しておくこと等、会社の設備と離れた場所に分散して保管しておくことも重要です。
- 資金の観点
被災後、一定期間は事業が中断してしまうのはやむ得ない事です。その際には、その期間中のキャッシュフローを把握しておき、保険や公的援助を受けることができないか、どの範囲で受けられるのかといった点を明確にしておきましょう。
- 組織体制の観点
被災後、平常であれば指揮権を有している人間が出社できないといった事態は当然に想定されます。そのため、被災後の組織体制をどのようにするか、また何を優先的に復旧させるのかといった点を明確にし、それが可能となる組織体制を考えておく必要があります。
具体的な策定方法や運用について

ここでは具体的な策定方法・運用について解説いたします。以下の手順に沿って策定を行います。
BCP対策の指針・目的設定
BCP対策をする指針や目的は何なのかを明確にしましょう。なぜBCP対策をするのかを最初に明示しなければ、その後の策定がスムーズに進みません。 災害やサイバー攻撃、SNSでの炎上といったリスクを想定した上で、BCP対策の指針を決めておく必要があります。
また、コストの面が問題なく、かつ自社で行う必要がない場合は外部に任せるということも一つの手です。
策定体制を整える
BCP対策は複数の事業部門に関わるため、部門横断型のプロジェクトチームを作るとよいでしょう。それぞれの事業部の意見を取り入れることでより実際に即したBCP対策が可能となります。
事業ごとに優先順位をつける
災害等が起きた後、どの事業から復旧させるかの優先順位を決めておきましょう。この際基準とするのは売上高なのか、復旧に動かなければ損失が大きくなる事業なのかなど、企業に合った基準で優先順位をつけましょう。
また、優先順位をつけた後で、実際に災害等が起きた場合のシミュレーションができるとベストです。できるだけ多くのケースを想定し、損失分析を事前に行えるとBCP対策の効果が高まります。
BCP実施基準や体制の整備
緊急時には冷静な判断が難しく、かつ十分な時間を取ることもできません。BCP対策の段階で実施の基準と体制整備を行うことが肝心です。具体的には以下を定めておきましょう。
- 実施基準:どんな基準でBCPを実施するのか
- 担当者:誰が実施の判断を下すのか、誰がどの事業を担当するのか
- 指示系統:誰から指示を受けてどう行動するのか
- 共有体制:全社員に周知できる体制になっているか
策定後:BCP対策を社内で共有し、運用していく
緊急時に全社員がアクセスできるようBCP対策マニュアルを作成しましょう。また、策定後はPDCAサイクルを回して運用していくことが肝心です。定期的にマニュアルをテストし、マニュアルに問題点や課題がないかをチェックしてマニュアルをアップデートしていきましょう。
法務業務におけるBCP対策とは

では、法務部門の業務においてのBCP対策とは、どういった業務を念頭に置くべきでしょうか。ここでは特にBCP対策が必要となる法務部門の業務を解説します。
主な法務部門の業務
法務部の業務については、人的資源の観点や、組織体制の観点など担当者に依存しやすい業務や、物的資源の観点から紙で保管している資料を扱う業務などについて、特に対策を考えることが必要になります。では法務部門の業務においてのBCP対策とはどのようなものがあるでしょうか。
①契約書審査業務
②法律相談業務
③契約書管理業務
④押印業務
①の契約書審査業務は、会社が締結する契約書の原案の作成や内容の審査を行う業務です。
②の法律相談業務は、主に事業部門などから契約や会社の方向性について法的な問題点の有無やリスクについて相談を受ける業務になります。
③の契約書管理業務は、締結済みの契約書の保管・管理を行うとともに、期限が切れそうな契約書の点検や更新などを行い適切な契約が締結されている状態を保つ業務です。
④の押印業務は、契約書を締結する際の押印作業や印鑑・印紙の管理などを行う業務です。
いずれの業務もこれまでは出社しておこなうことが前提となっており、特に①や②については担当者が出社できなくなった場合には、担当者以外に内容が分らないため業務継続が難しくなってしまうという事態にもなりかねません。
法務部門の業務におけるBCP対策の必要性
では、先ほどご紹介した業務とBCP対策は具体的にどのような関係があるでしょうか。
①契約書審査業務の場合
契約書審査業務については、依頼部門や事業部門の担当者とやりとりを行い、契約書の作成や審査を行います。こうした情報が部門内で共有されていない場合、例えば地震などの災害時に担当者がケガをし、出社ができなくなってしまうということも想定されます。その際には、情報が無いため他者へ引き継ぐことができず、再度事業部門からヒアリングを行うまで業務が停滞してしまうことになります。
②法律相談業務の場合
法律相談業務についても、事業部門からヒアリングを行い法的な回答を行うことになりますが、これも①と同様に担当者が出社できなくなってしまったり、業務が困難な状態になってしまうと、再度ヒアリングを行うまで業務が停止してしまうことになります。
③契約書管理業務
契約書管理業務では、締結済みの契約書の管理を行うことになりますが、紙の契約書で管理・保管を行っており、火災や水害により保管していた契約書が一部消失してしまった場合には、契約書の保管や更新時期の確認などができなくなってしまい、相手方と協議を行った上で同一の内容の契約書を再度締結するなどの対処が必要となります。
こうした処置を行うまで契約の内容を確認することができないという事態が起きてしまいます。
④押印業務
押印業務では、印鑑を使用することになりますが、こうした印鑑や印鑑カードが災害によって消失してしまった場合には、手続きを行い、新しい印鑑ができるまで新たな契約の締結などができなくなってしまいます。
BCP対策におけるリーガルテックの活用方法・想定事例

では、こうした課題を解決するためにはどのようなBCP対策が考えられるでしょうか。ここからはBCP対策のためのリーガルテックの導入の有用性について具体的なケースを踏まえて解説します。
ケースごとにBCP対策に有効なリーガルテックツールをご紹介
ケース①
法務担当者が交通事故に遭い、業務に復帰することが難しくなってしまった。
こうしたケースでは、法務担当者が担当していた契約書審査業務や法律相談業務について停滞が生じる可能性があります。契約書審査や法律相談の内容を簡単に記録・情報共有出来る仕組みを導入することで、情報を一元化し引継ぎなどもスムーズに行えるようになります。
▼有効なツール
- ContractS CLM

ContractS CLMは、契約業務に関するプロセスを一つのシステム上で管理するためのCLMツールです。契約作成の依頼から承認までのプロセスを可視化し、契約業務に関わる部門間で、契約関連業務のステータスや作成までの経緯を共有できます。早期の復帰が難しい法務担当者に代わって他のメンバーが引き継ぎやすくなる効果が期待できます。
参考:ContractS CLM(コントラクツ CLM)| ContractS株式会社
- DocuSign CLM

DocuSign CLMは、契約書作成の依頼や交渉の過程等を一元管理することができるCLMツールです。そのため先ほどのような場合でも、引き継ぎ担当者がすぐにこれまでの交渉の経緯などを確認した上で、スムーズな契約書作成が可能となるという効果が期待できます。
参考:契約ライフサイクル管理システム | DocuSign CLM
ケース②
オフィスの移転を行った際に契約書の原本を紛失してしまった。
オフィスや本社を移転した際に、物を紛失するのはよくある話ですが、契約書の原本を紛失してしまうというのもあり得る話です。こうしたケースでは、契約書原本を一カ所に集約して保管するようにし、その他の天災からも保護できるように堅牢な保管施設に入れておく等の対応が考えられます。それ以外にも、電子契約を導入し、紙ではなく電子ファイルの形式で契約書を保管しておくことで紙の契約書の数を減らす又は無くしていくことも有効なBCP対策といえるでしょう。
▼有効なツール
- クラウドサイン
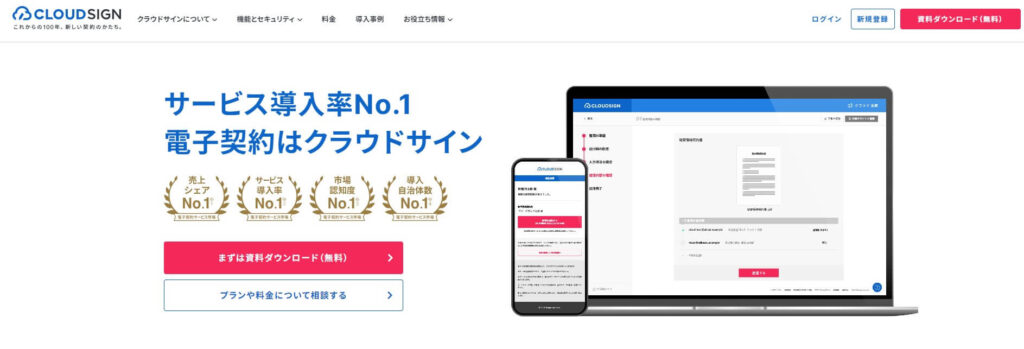
クラウドサインは弁護士ドットコムが提供している電子契約サービスです。そのため、市場での認知度が高く、契約送信件数第一位の実績を誇っています。電子契約サービスを導入し、紙ではなく電子ファイルの形式で契約を締結することで、先ほどの例のようなオフィス移転だけでなく、災害などの際にも契約書原本を紛失してしまうというリスクを避けることが可能です。
参考:クラウドサイン | 国内シェアNo.1の電子契約サービス
- リーガレッジ

リーガレッジは契約書を電子ファイルとして登録・管理できるサービスです。紙で契約書を締結した場合でも、その後電子ファイルとして管理することで契約書の紛失リスクを大きく下げることが可能です。また、契約書の更新管理や期限管理機能を用いることで、契約書の更新等が必要な時期に通知を受けることができ、コンプライアンスの向上にも役立てることができます。
参考:Legaledge(リーガレッジ) | 法務チームの為の契約ナレッジマネジメントシステム
ケース③
感染症の影響で出社できる人数に大幅に制限がかかってしまい、押印業務に長期間を要するようになってしまった。
新型コロナウイルス感染症が流行していた際に、政府はオフィスへの出社人数を制限するように求めていました。こうした状況で、各企業で課題となったのが押印業務です。印鑑がオフィスにある点や、押印までの稟議や承認が出社を前提としていたため、押印までに非常に時間がかかるという事態になっていました。こうした事態への対策として有効なのが、電子署名や電子押印など電子契約の導入です。
▼有効なツール
- GMOサイン
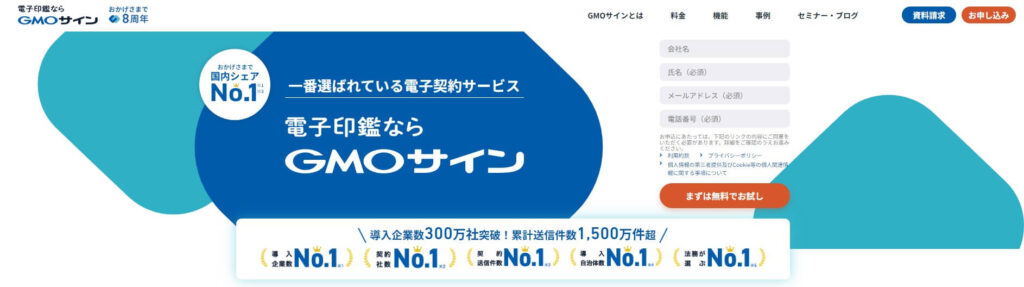
GMOサインは、導入企業数が190万社を超える国内導入数一位の電子契約サービスです。同サービスは、電子署名にかかる1件当たりの送信料が110円となっており、コストパフォーマンスが良いという特徴があります。GMOサインを導入することで費用を抑えつつ、スムーズな契約締結が可能となる点は同サービス導入のメリットといえるでしょう。
参考:電子契約なら電子印鑑GMOサイン|導入企業数No.1の電子契約サービス
- Docusign

Docusignは、アメリカの企業が提供する電子契約サービスです。電子契約は自社だけでなく相手方も利用する必要があるため、特に海外の取引先が多い会社では導入のメリットの多いサービスといえるでしょう。
参考:ドキュサイン | 電子署名と契約ライフサイクル管理業界のNo.1
契約書管理のBCP対策はリーガレッジで
契約書管理業務については、契約書管理システムの導入によって紙の契約書の管理を電子化し、法務部門のBCP対策を行うことができます。
紹介したツールの一つ、「Legaledge」は、契約書のデータベース化もPDFファイルのドラッグ&ドロップで可能など既存の契約書の電子化や管理も簡単に行うことが可能です。
契約書管理業務や契約書に関する業務のBCP対策をご検討される際には是非リーガレッジの導入をご検討ください。